|
|
 |
| 高裁判決確定を受け、支援者に謝辞を述べるとともに佐野南海交通労組の組合員を激励する権田委員長=5月14日、大阪・自交会館 |
第一交通は01年に佐野南海交通などを買収、不当な賃下げをはじめ数々の攻撃にも関わらず団結を維持してたたかい続ける組合をつぶすために03年に同社を偽装解散して全員を解雇していました。
 |
| 全面解決までたたかう意志を固め合う組合員と支援者たち |
大阪高裁は昨年10月、組合つぶしという違法な目的のために子会社を解散させた第一交通本社の責任を全面的に認める判決を出していました。最高裁は5月1日、第一交通側の上告を棄却、高裁判決が確定しました。
5月14日の勝利報告集会には当該組合員ら100人以上が参加。小林弁護団や裁判で意見書を執筆した近畿大法科大学院の西谷教授は、「法人格否認の法理」で親会社の責任を認めた画期的な判決で、タクシーだけでなく戦後の重要な労働判例として今後労働法の教科書には必ず載る判決、と評価しました。
佐野南海交通労組の堀川委員長は、裁判に勝ったが気をゆるめず全員の職場復帰、最後の勝利まで闘いぬきたい、と声を詰まらせながらお礼と決意を述べました。
佐野第一交通解散解雇事件の組合側勝訴が確定
弁護士 藤木 邦顕
 |
| 藤木弁護士 |
第一小法廷は、同じ解散解雇の保全事件で雇用関係は受け皿として進出させた御影第一との間にあるという大阪高裁の保全抗告決定を支持していましたので、会社側の上告および上告受理申立が同小法廷に係属したと知ったときには、弁護団としては大阪高裁判決の見直しの可能性もあると警戒しました。今回の決定は、会社側の言い分は上告理由にもならず、最高裁としては重要な法律上の問題を含むと解さないとしたもので、大阪高裁の本訴の判決が完全に支持されました。
親会社による子会社の解散について、法人格否認の法理を使って労働者の雇用を守ることを認めた判決は、1970年代には見られましたが、80年代以降極めてまれになっていました。今回の最高裁決定は、組合つぶしのために子会社を解散するという親会社の無法は許されないとした点で従来の理論を再確認したものですが、企業の横暴が広がり、雇用が失われることの多い現代で、親会社の雇用責任を認めた点では労働者・労働組合の闘いに広く大きな武器を与えたことになります。
最高裁決定後、会社は組合員をどこで、いかなる条件で働かせるのかまだ明らかにしていません。組合・弁護団は、雇用が実現する時まで、さらに会社を追及する決意です。
規制緩和の被害見る姿勢なし
「賃金等は労使交渉で」と切り捨て
東京地連 国賠裁判 組合側訴え退ける不当判決
 |
| 判決後記者会見する原告団=5月16日、東京地裁内司法記者クラブ |
判決は、運賃割引と運転者の賃金低下の間には関連がない、運転者には訴える資格がない――として訴えをはねつけ、「賃金等の個別的な労働条件は企業内の問題として労使交渉等で決着していくべき問題」と切り捨てています。また、審理を一方的に打ち切るなど裁判長の異常な訴訟指揮も目立ちました。
判決後の記者会見で、原告と弁護団は、「裁判所は運転者の声を聞かず規制緩和の被害を見ようという姿勢がなかった」「形式的で非常に冷たい判決」「なんでも労使交渉で処理しろというのは非常識」と厳しく批判、控訴することを明らかにしました。
同時に、裁判をたたかうことによって、これまで知られなかったタクシー産業とそこで働く運転者の実態が、マスコミなどに大きく取り上げられるようになり、規制緩和がもたらした格差社会への告発として大きな役割を果たし、行政の姿勢にも大きな影響を与え、事実上の規制緩和見直しへの道をひらいてきたことを示して、安心・安全なタクシーの実現を求め引き続き全力でたたかうことを表明しました。
| この成果を全国に |
大阪・佐野南海交通労組
組合壊滅目的の偽装解散と認定
組合員は親会社の責任追及できる
最高裁で確定した第一交通事件の大阪高裁判決(07年10月)は、第一交通本社の責任を明確に認定、黒土会長、田中社長も共同不当行為責任を負うとして、以下のように判示(要旨)しています。
◇第一交通は、新賃金体系の早急な導入だけを企図し、(話し合いなど)本来あるべき道筋を当初から一切無視して、もっとも違法性の強い佐野第一を解散し組合員らを全員解雇するという極めて極端な手段を自ら選択した。法治国家である日本において会社や事業を経営する以上、経済的に有利であるからという理由から違法な手段を選択することが許容されていないことは当然である。
◇親会社である第一交通による子会社である佐野第一の実質的・現実的支配がなされている状況の下において、組合を壊滅させる違法・不当な目的で子会社である佐野第一の解散決議がなされ、かつ、偽装解散であると認められる場合に該当するので、組合員である原告らは、親会社である第一交通による法人格の濫用の程度が顕著かつ明白であるとして、第一交通に対して、佐野第一解散後も継続的、包括的な雇用契約上の責任を追及することができる。
登録取消し後は指定地域で乗務できず
国交省
6月14日より運転者登録制度実施
国交省は運転者登録制度の6月14日実施にともなう政省令の改正案、運転者の登録取消処分の基準案等をまとめ、5月16日に自交総連にも説明がありました。
6月14日時点で既存と新規区分
新設の指定地域では、運転者は運転者登録を受けなければタクシーに乗務できなくなります(東京・大阪はすでに実施されているので、新たな登録等は必要ない)。
6月14日現在で選任済みの運転者は12月13日までに講習(3時間程度、自社講習可)を受けて登録することが必要で、病気休職中等でも期間内の講習が必要となります。
6月14日以降に新たに雇用・選任する運転者は、新規の講習(2日、11時間以上、効果測定あり)を修了して登録することが必要です。
処分は国(運輸局)が行う
登録後違反行為等があると、命令講習、登録の効力停止、登録取消し(一定期間再登録禁止)の処分がされることになります(下表)。登録取消しになると、処分された地域以外でも全国の13指定地域内では乗務できません。
処分は、登録実施機関ではなく、国土交通大臣(運輸局長)が行い、聴聞の場で弁明の機会を設けて公正性を担保するとしています。
道交法違反の免許停止で事実関係を争っている場合などは聴聞の場で考慮するとしています。
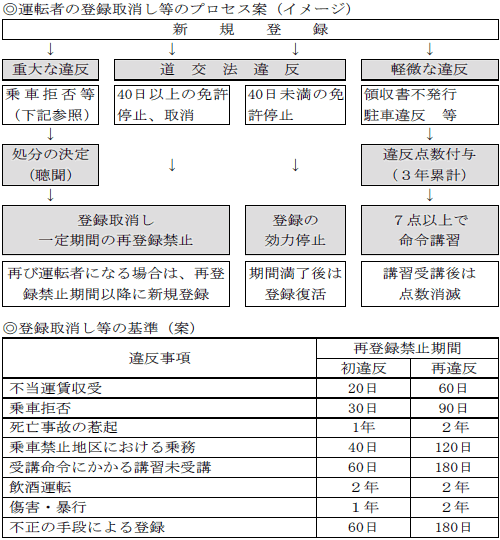
各地で自交総連に期待する声
東北ブロック
青森で組織拡大宣伝行動実施
 |
| 乗務員から聞き取り調査を行う宣伝行動参加者=5月19日、弘前市内 |
宣伝には青森地連の仲間と福島地連・山崎良博委員長、山形地連・武田幸夫委員長、宮城地連・大島治吉執行委員らが参加、弘前・青森・八戸の3都市で自交総連への加入を呼びかけました。
各地とも自交総連の活動に期待する声が多く聞かれ、機関紙を手渡すと早速読み入る乗務員たちの姿が見られました。
 |
| 宣伝カーからの乗務員への訴え=5月20日、青森駅前 |
あるタクシー乗り場では、客待ちスペースに並ぶために空ができるまで何度も出入りを繰り返すタクシーが見られました。
タクシー台数が人口250人に1台と極端な供給過剰に陥っている弘前を象徴する光景で、我々の活動の大切さを痛感させられました。
仲間を増やして要求実現を
10回にわたって自交総連を紹介
 |
| 自交総連への加盟を呼びかけた未組織宣伝キャラバン行動 |
タクシーは、国民にとってなくてはならない公共的輸送機関です。そういう意義ある仕事をしているのに、あつかいは人なみ以下でいいはずがありません。
自交総連は、そのことをつよく主張してたたかい、大きな成果をかちとってきました。
仲間が増えれば、もっと多くの要求を実現することができます。
自交総連をもっと「つよく」「大きく」――3万人の自交総連をめざして、いまこそみんなで力を合わせるときです。
そこで組織拡大にむけ、本紙では、未組織の仲間にも自交総連を紹介できるように、労働組合の意義やこれまでかちとった政策闘争などを次回より10回にわけて連載します。
今後の掲載予定内容
(1)規制緩和とハイタク労働者の労働実態
(2)会社のいいなりで労働者はよくなるか
(3)高齢化するタクシー労働者と不安定雇用労働者の権利
(4)労働者の権利と労働組合
(5)みんなの要求はみんなで実現
(6)自交総連とは?
(7)社会的水準の労働条件確立をめざす政策とこれまでの政策闘争の成果
(8)労働組合と政治、政党との関係
(9)自交共済・自交共済年金制度の役割
(10)組織拡大とナショナルセンターの役割
公共交通の安全・安心が国民的ニーズ
第6回交通問題研究集会に158人
 |
| あいさつする安部会長=5月24日〜25日、伊東市 |
主催者あいさつで安部誠治会長は、「この間、公共交通の安全・安心問題が国民的ニーズとなってきた。交運研の政策が確実に実現している。この集会を期に、さらに新たな政策実現を」と呼びかけました。
記念講演は、上岡直見氏(環境政策研究会)から「持続可能な社会と交通の貢献」でした。基調報告では「交通政策の提言2008の概要」が川村雅則准教授(北海学園大学)からありました。
2日目は、3つの分科会で議論。自交総連は第2分科会(都市交通)に全員が参加し、現場の実態報告、規制緩和後の闘い、タクシー運転免許法制化の課題などの発言をしました。