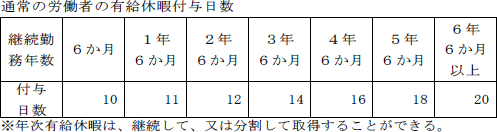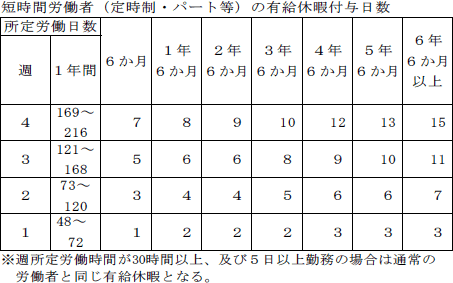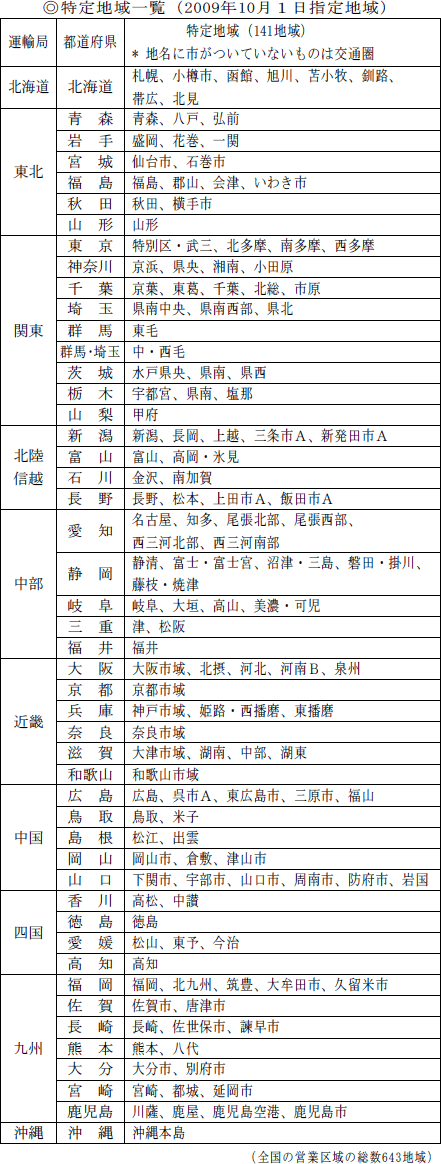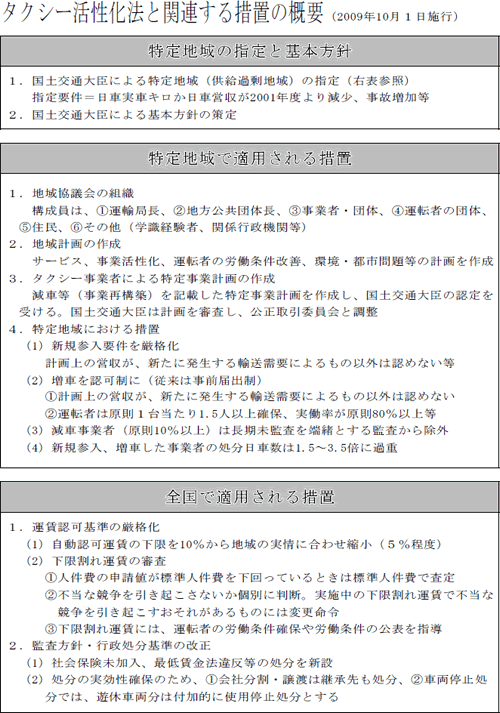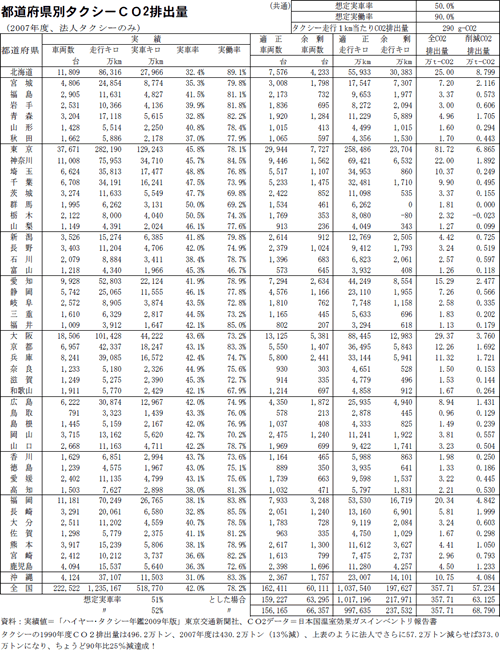|
|
 |
| 国交省前で減車の文字を掲げアピールする自交総連の仲間=08年4月 |
基本方針では「特定地域は、供給過剰の進行や過度な運賃競争により…タクシー運転者の労働条件の悪化が進行」しているとし、地域計画では「供給過剰の解消や過度な運賃競争の回避、運転者の労働条件の改善・向上、タクシー車両による交通問題の解消のための対策について定めることが求められる」と明記されています。
この方針に従い、協調的な減車の方法などが定められるとともに、その実効性確保と全国的な労働条件改善のための措置として、運賃認可基準、監査方針・行政処分の改正が行われました。
減車を実現するためには、こうした規定を生かした、各地域での運動ととりくみが求められます。
減車でCO225%削減
実車率アップでムダ排除
タクシー労働者の労働条件を改善するためには大幅な減車が不可欠ですが、減車はCO2削減の面でも有効です。
自交総連の試算では、タクシーを実車率が50%となるように減車(6万台、27%)した場合、年間57万トンのCO2が削減でき、タクシー全体の排出量を373万トンにすることができます。これは1990年度の排出量496万トンの25%減に相当し、鳩山首相が国連で表明した2020年までに25%減の目標を、タクシー分野では一気に達成できることになります。
タクシーの減車は、乗客を探して空車でムダに走り回る走行距離が削減されるだけで、乗客の利便性、乗りやすさに悪影響はありません。同じ労働時間で売上が上がるため、タクシー労働者の労働条件は賃金・労働時間とも改善され、安全性・サービスも向上します。
自交総連では新法を活用して、各地域でできる協議会に積極的に参加して、事業者が協調して減車するようにつよく求めていくことにしています。
【試算の根拠】(下表参照)
CO2削減量は都道府県ごとのデータが揃う法人タクシーについて試算したもの。個人タクシー(07年度末4万5486台)、ハイヤー、患者輸送車等は計算からは除外してある。
全国には、22万2522台のタクシーがあり、その全走行キロは年間123億5167万キロである。このうち乗客を乗せて走っている実車キロは51億8770万キロで、実車率は42%である。実働率は1日ごとに稼動した車両の割合で、78・2%というのは、2割以上の車が稼動せずに車庫で眠っているということである。
想定実車率50%、想定実働率90%として、実績の実車キロ51億8770万キロを賄うに足りるタクシー台数は16万2411台で余剰車両数は6万0111台(遊休車両も含まれる)となる。同様に適正な走行キロは103億7540万キロ、余剰走行キロは19億7627万キロとなり、この19億7627万キロを削減することにより削減できるCO2は57・234万トンとなる。
1990年度のタクシーのCO2排出量は496万トン(個人タクシー等も含む)、2007年度は430万トンですでに13%減となっているが、さらに上記57万トンを減らせば、373万トンになり、1990年比25%減となる。
賃金体系の改善重点課題に
福島第15回大会
大会では、社会的水準の労働条件確立、権利拡大をめざすために、状態悪化に歯止めをかけ、累進歩合制度の廃止など賃金体系の改善を重点課題としてとりくむことを決め、組織の強化拡大では、一桁組合からの脱却、少数派から職場内多数派への具体化、個人加盟方式の自交労働者地域労組結成をはかり組織的発展をめざすことにしています。
新法を生かし減車の実現を
東京第119回大会
 |
| 熱心に聞き入る参加者=9月30日、東京・亀戸文化センター |
大会では、主催者を代表して飯沼委員長が「タクシー新法が施行され、地域協議会では中心議題である減車について適正台数が示されます。協議会まかせではなく、新法を継続的な運動で実効あるものにしていこう」とあいさつしました。
組合の力発揮し権利守ろう
広島第44回大会
 |
| 広島地本第44回定期大会=10月5日、ふくやま市民交流館 |
委員長=中谷広夫▽副委員長=切田明▽書記長=内谷富雄
あなたの職場に有休はありますか?
有休は法律上、労働者に当然に発生する権利です
継続6か月勤務で有給休暇
労働基準法では、年次有給休暇は、雇い入れの日から(1)6か月間継続勤務し(2)全労働日の8割以上出勤した労働者に、(3)継続し、又は分割した10労働日の休暇を与えなければならないとしています。
「継続勤務」とは、職場での在籍期間を意味しています。また、実態が継続するときは通算されますから、定年退職者が引き続き再雇用されている場合や期間雇用者の雇用契約が更新され、引き続き使用されている場合なども6か月間の継続勤務ということになります。
業務中負傷の休業も労働日
「全労働日の8割」とは、実際に労働する日をいい、労働協約、就業規則等で定められた日がこれに該当しますが、“8割以上出勤”を計算する場合には、業務中に負傷し休業した日や育児・介護休業をした日、また、年次有給休暇を取得した日も出勤した日となります。
また、年次有給休暇の権利は、法律上当然に労働者に発生するため、使用者がその権利を与えないということは許されません。そのため、「うちの職場に有休なんてない」というようなことはないのです。
有休中の賃金は就業規則で
年次有給休暇中の賃金には(1)平均賃金、(2)所定労働時間労働した場合に支払われる賃金、(3)健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額の3つがあり、どの方法によるかは事前に就業規則に定めておく必要があります。