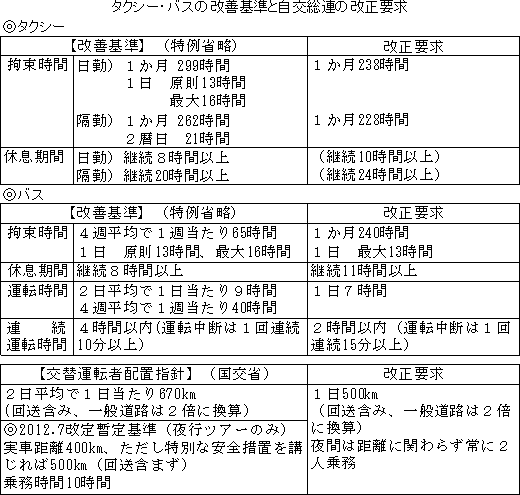|
|
 |
| 活性化法施行前、駅前でひしめく客待ちのタクシー=2009年3月1日、神奈川県内 |
【解説】タクシー活性化法は09年10月1日から施行され、営収等の指標で供給過剰と判断された142地域が3年間の期間で特定地域に指定されました。
特定地域では、地域協議会がつくられ、タクシー事業の適正化のためには運転者の労働条件改善が必要であるとして、参入・増車はストップした上で、減車や需要喚起策などの地域計画を作成して実施してきました。
3年間の期間が過ぎ、国交省の調べでは、全国で2万3000台以上(12・4%)の減車がすすみ、日車営収には2年連続で回復がみられるなどの改善があったとしています(前号既報)。
しかし、各地域の指標は依然として特定地域指定要件に合致しているため、10月1日付で再指定されたものです。
再指定された地域では、改めて地域協議会で地域計画を論議、策定することになります。その際、目的となるのは、運転者の労働条件の改善です。
労働条件は、いまだに規制緩和前の状態に達していないのが実情であり、この改善が十分に図られるように、新たな減車や需要の喚起などの計画をつくって実行していく必要があります。
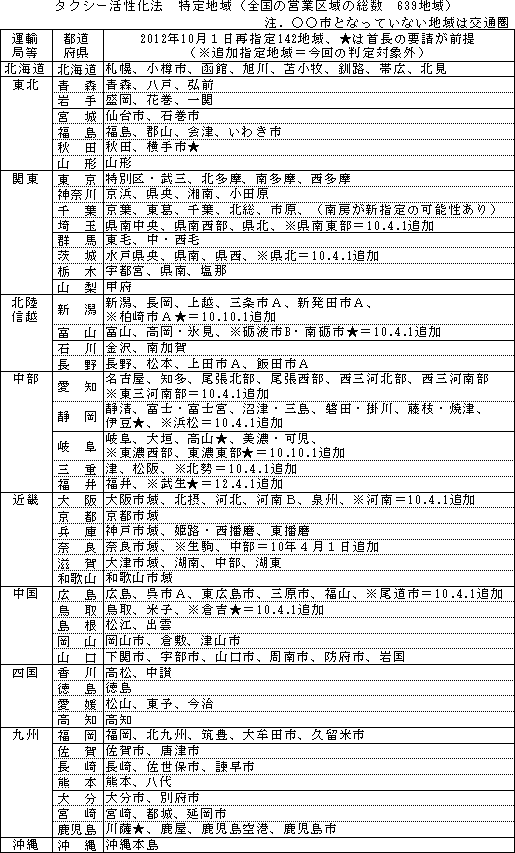
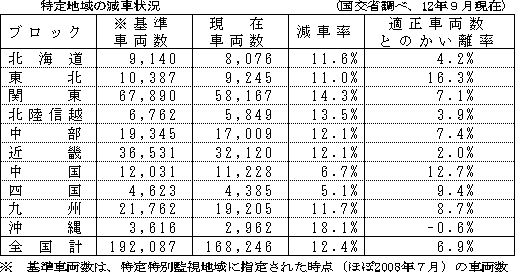
3か月で12人増やす
月2回宣伝、声掛け
東京・不二タクシー労組
 |
| 機関紙を配布する不二タクシー労組の仲間=9月4日、会社構内 |
不二タクシー労組は2012年春闘で組織内他労組と共闘して会社の合理化を阻止しました。しかし近年、定年退職や無線グループ再編などによる他社への移動などで組織減の傾向にあり、今後のたたかいにも影響するおそれがあるため、執行部が議論。組織拡大を重点課題としてとりくむことを確認し、役員が中心となって声掛け運動を展開しています。
また、月に2回東京地連と本部の機関紙、東部ブロックの機関紙を配布して、未組織労働者に組合の運動を知らせています。
その結果、6月に2人、7月に3人、8月には7人が新たに組合員となり、着実に組織を増やしています。
泊り込みで8人増
全国からの支援を有効活用
宮城・仙台タクシー労組
 |
| 組織拡大の成果を報告する仙タク千代窪委員長と鴇(とき)副委員長=7月25日、宮城地連事務所 |
仙台タクシー労組は、全国の仲間から寄せられる10円カンパを有効に使おうと、組織拡大委員会を構成し、議論を重ねてきました。今回の行動では、執行部員全員が組合事務所に泊まり込み、日勤、夜勤、隔日勤務の未組織労働者約30人に声を掛け、組合の重要性を説明しました。
執行委員の高橋さんは、「以前は声を掛けても『組合費が高すぎる』『メリットがない』などと言われて相手にしてもらえなかったが、ねばり強く説明することで仲間を増やすことができた。この成果に自信を持ち、これからも組織拡大にとりくんでいきたい」と話しました。
国民的共同のとりくみ強化を
全労連運動の前進へ
民間部会 第21回総会
 |
| 12年度活動方針などを決た第21回総会=9月20日、東京・医療労働会館 |
来賓の全労連・大黒議長は、橋下維新の会の保守タカ派という本質を組合員に知らせていこうなどと政治情勢に触れて全労連運動の前進を訴えました。
20周年を迎える民間部会の記念事業の計画、公務の仲間との連帯、国民的な共同のとりくみを強化することなどを確認しました。
| この成果を全国に |
香川・丸亀東讃交通労組
職場復帰の和解かちとる
定年後の継続雇用拒否で
高松地裁
【香川】香川地連丸亀東讃交通労組は、委員長の福本康嗣さんが60歳の定年で継続雇用を不当に拒否されていた事件で9月12日、高松地裁で和解をかちとり、福本さんは21日から職場復帰しました。 同社では定年は60歳ですが、本人が希望すれば65歳まで継続雇用されることになっています。ところが福本さんに限って「勤務成績が基準に達しない」などとして10年5月に継続雇用が拒否されました。これは組合委員長である福本さんを排除することをねらった不当解雇であるとして裁判に訴えてたたかってきました。
裁判では、選別基準を定めた労使協定に調印したという労働者代表も正式に選ばれていないこと、福本さん以外は勤務成績に関わらずすべて継続雇用されていることなどが明らかになるなか、裁判長のすすめで和解となりました。
職場復帰した福本さんは「自交総連や県労連の仲間の支援で職場に戻ることができました。ありがとうございました。これから組合員を増やしていきたい」と語っています。
将来像にむけた運動強化を
福島第18回大会
 |
| 次年度方針を決めた福島地連第18回大会=9月17日、福島市サンライフ福島 |
新年度方針では、深刻な状態悪化がつづき、特定地域の再指定となっている事態に、すべての労働者との共同を強化し労働条件の改善をはかるため、全員参加の新たな運動の展開をはかることや、職場活動の活性化と次代を担う幹部を育成し、組織の強化拡大にとりくみ、将来像にむけた運動を強化することなどを確認しました。
橋下市長維新の会
政策の中身は規制緩和への回帰
競争で貧困と格差拡大
「維新八策」の内容を検証
橋下大阪市長が率いる大阪維新の会は、「日本維新の会」を発足、国政に進出することを発表ました。国民の政治への不満を吸収して人気を集めているといわれますが、その政策の中身を検証してみます。 【解説】大阪維新の会が公表している「維新八策」の要点は左表のとおりです。その特徴は、規制緩和をすすめ格差と貧困を拡大した小泉時代への回帰といえます。
規制緩和がどういうものだったかは、自交労働者なら身にしみています。競争すればすべてうまくいくといってタクシーもバスも規制緩和されましたが、その結果は、過当競争による事故の増加、際限ない労働条件低下というものでした。
大企業・多国籍企業だけが儲かり、ほとんどの国民は格差と貧困におちいり、青年は正社員の職を得ることもできなくなりました。
それを再び露骨に実行しようというもので、公務員を「敵」にしたてて、国民の不満を刺激、一気に強行しようとする手法には警戒が必要です。
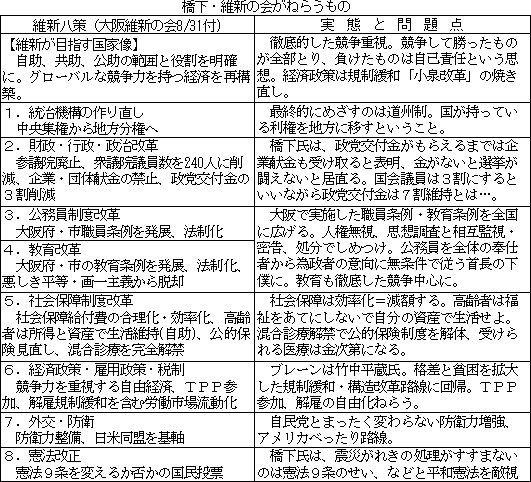
自交総連の基本政策
(4)労働時間等の改善基準
通達では実効性ない 法制化し拘束力強く
タクシーもバスも労働時間が異常に長い問題業種で長時間労働が交通事故にも結びつくことから、他の業種にはない労働時間の規制があります。厚労省が告示している「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」がそれで、関連通達と合わせて改善基準といわれています。 改善基準は、もともとは12・27通達といって、79年に通達として出されました。しかし、拘束時間が長すぎるという欠点とともに、通達であるために拘束力が弱く実効性がないという問題がありました。
自交総連では86年に「27通達法制化闘争」にとりくみ、中身の改善と法律にして罰則もつけることを要求、法制化までは至りませんでしたが89年に通達から告示となり、97年には労基法の改正に合わせて拘束時間が短縮されました。
しかし、依然として拘束時間は長く、罰則もありません。
経営者は法律で縛られない限りなかなか時間短縮をしようとしません。ひきつづき、より時間短縮して法制化するように求めていくことが大切です。